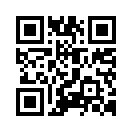2016年01月23日
ヘチマの花が
どうも、校長のアタです。
ニュースで寒波襲来の話題を報じています。「百年寒波」なる言葉も聞きました。昨日、学校に来られた新聞記者さんも日、月曜日は
「奄美初の雪」を期待して湯湾岳(奄美大島で一番高い山)に待機すると言っていました。
ところが久慈校では夏を代表する植物のヘチマがまだ元気に育っています。

近くでよく見てみると、

花が次々に咲いています。
みなさんはヘチマのたわし、あるいはお風呂でのあかすり代用として枯れたヘチマの実を使ったことがありますか。
ヘチマの実は枯れると糸の固まりみたいな形状になりますね。
だから昔からヘチマは「糸うり」と呼ばれていました。「いとうり」がやがて「とうり」と短縮されました。そして、この「とうり」の「と」はいろは歌の
「いろはにほへとちりぬる…」で見ると「へ」と「ち」の間にあることが分かります。そこから、「へ」と「ち」の間、つまり「へちま(間)」となったそうです。
※諸説あり
奄美や沖縄ではへちまを「ナーベラ」、「ナベラ」、「ナブラ」などと言いますが、「鍋を洗うタワシ」という意味があるようです。
さてさて、明日、あさっては奄美でも雪が見られるかな。
ニュースで寒波襲来の話題を報じています。「百年寒波」なる言葉も聞きました。昨日、学校に来られた新聞記者さんも日、月曜日は
「奄美初の雪」を期待して湯湾岳(奄美大島で一番高い山)に待機すると言っていました。
ところが久慈校では夏を代表する植物のヘチマがまだ元気に育っています。
近くでよく見てみると、
花が次々に咲いています。
みなさんはヘチマのたわし、あるいはお風呂でのあかすり代用として枯れたヘチマの実を使ったことがありますか。
ヘチマの実は枯れると糸の固まりみたいな形状になりますね。
だから昔からヘチマは「糸うり」と呼ばれていました。「いとうり」がやがて「とうり」と短縮されました。そして、この「とうり」の「と」はいろは歌の
「いろはにほへとちりぬる…」で見ると「へ」と「ち」の間にあることが分かります。そこから、「へ」と「ち」の間、つまり「へちま(間)」となったそうです。
※諸説あり
奄美や沖縄ではへちまを「ナーベラ」、「ナベラ」、「ナブラ」などと言いますが、「鍋を洗うタワシ」という意味があるようです。
さてさて、明日、あさっては奄美でも雪が見られるかな。
Posted by kujikko at 06:48│Comments(0)
│久慈の宝物
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。